書 評
長浜市三田町に所在する三田村氏館跡は、2006年1月26日に国の史跡に指定されました。居館に伴う建造物は残されておらず、土塁と堀が残されているに過ぎません。その城館跡が小谷城跡(最後の城主・浅井長政)や観音寺城跡(最後の城主・六角義弼)などの大規模な戦国時代の山城跡と同様に、日本の歴史にとって重要な遺跡として史跡に指定されたのです。
さて、本書の著者は三田村氏館跡の近くに生まれ育ちました。その郷土愛が本書の一行一行にあふれています。三田村の歴史を弥生時代から掘り起こされている大著です。清水さんは中世の三田村を知るには古代からの歴史を知る必要があると知っておられたのでしょう。
本書の中核をなすのは三田村氏館の館主である三田村氏一族の歴史です。ここでは三田村氏歴代の歴史を縦軸に、京極氏、浅井氏との関係を横軸に、まさに近江の中世史を概観することができます。さらに三田村の農村や農民との関係にも触れられ、中世の在地領主の在り方がわかりやすく描かれています。
三田村氏館跡は湖北の典型的な在地領主の居館跡で、村落の中心部に位置しており100㍍四方の土塁と堀を巡らせた構造です。近世以降多くの居館跡は館主が不在となり、館跡は田畑に変わり、その歴史とともに痕跡を失ってしまいます。ところが三田村では領主が滅んだ後も館跡が真宗大谷派・傳正寺(1715年創建)の境内地となり、奇跡的に土塁や堀が残されました。また、三田村氏館跡は単郭ではなく、館跡の北側にも主郭と同じ規模の曲輪が存在しており、複郭構造であったことがわかっていました。
三田村の歴史は三田村の方々に知ってもらうことがもっとも大切です。地元で生まれ育った清水さんによって執筆された本書はまさにうってつけの好著です。本書では歴代の三田村氏の歴史を物語ることによって、遺跡としての三田村館跡を生き生きとしたものとしてくれています。まずは地元の方々、特に子どもたちに読んでもらいたいと思います。清水さんは子どもにも読めることを狙って読みやすく執筆されています。子どもたちに豊富な歴史のあるまちに住んでいることを知ってほしいと思います。そして全国の方々にも読んでもらいたいと思います。地元の歴史を知り、それを誇りと自信にすることからまちづくりは始まります。郷土愛の醸造に本書をお薦めします。


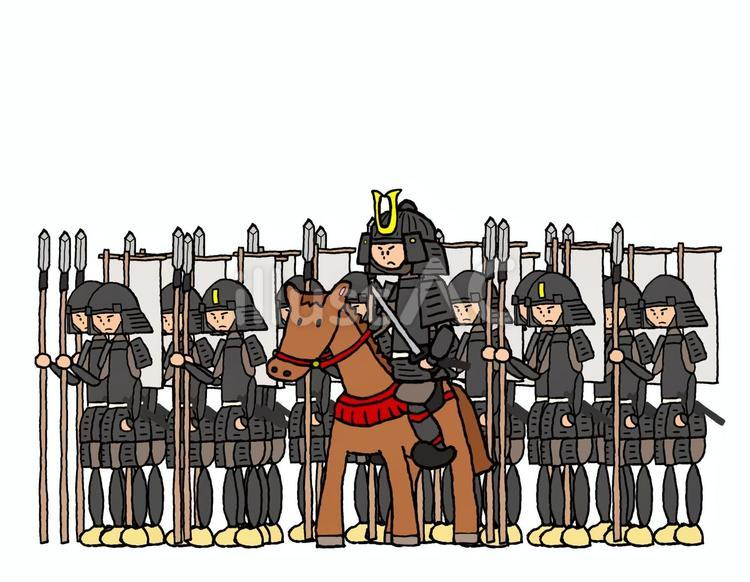
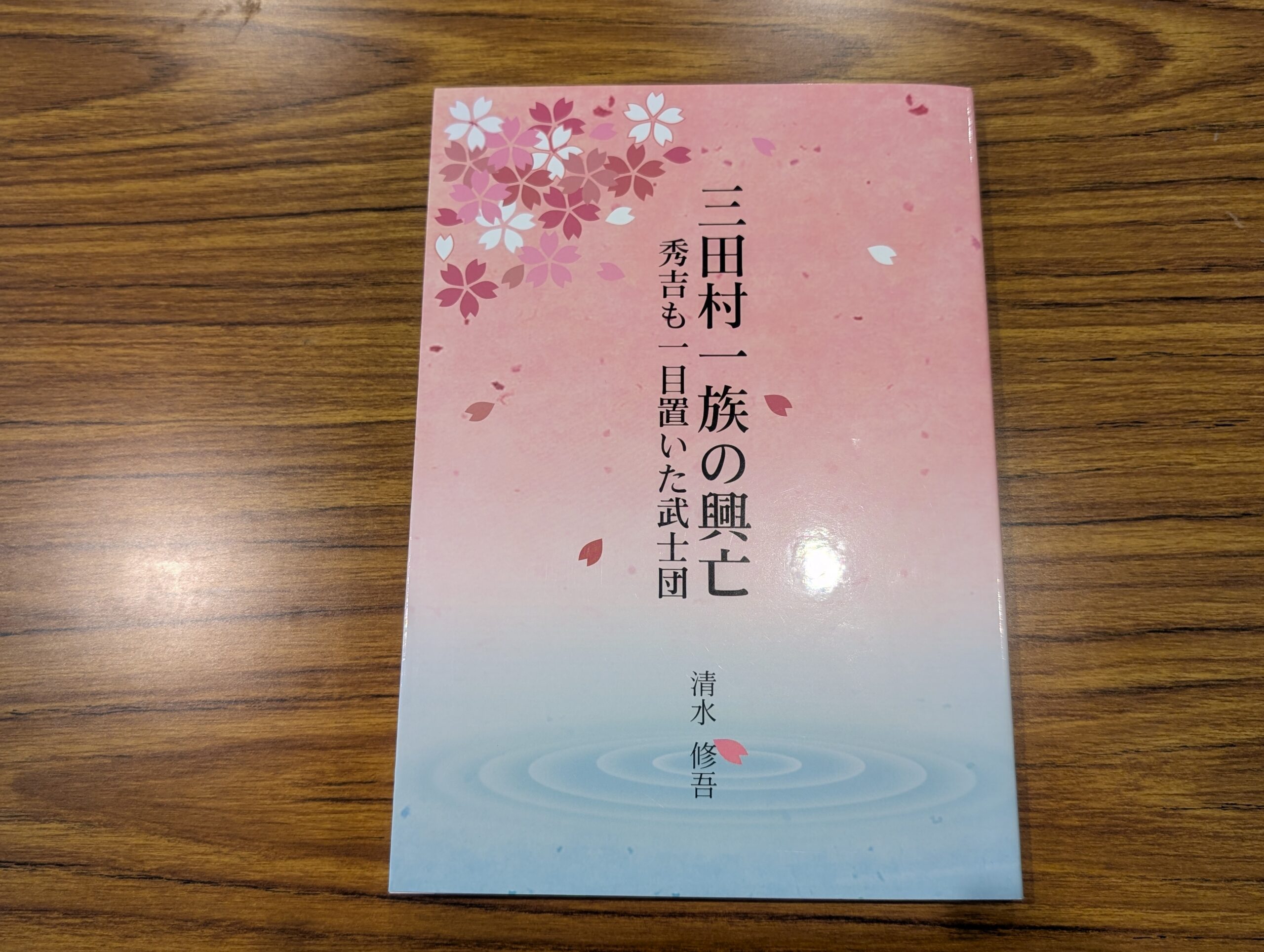
新聞記事(クリックしてご覧下さい):https://www.chunichi.co.jp/article/537196 パスワードmita1789
