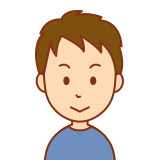
湖北・三田村一族の歴史を描く名著!
滋賀・北近江に刻まれた、もうひとつの歴史がここにある。
※下記の写真画像はマウスオーバーで拡大表時する事が出来ます。画像をより詳細にご覧いただけます。


最盛期の三田村城(1560年頃)→1級資料に基づいてC.Gで作成した「三田村城」復元図(1560年頃)。外堀は南流の「姉川」と北流の「草野川」から導水、万一の場合に備えた危機管理が見える 。


三田村家 歴代城主一覧
| 初代 | 三田村左衞門尉幸弼 | 源頼朝より地頭職を拝命して赴任。官位は従五位下「三田村左衞門尉」で、代々の城主は左衞門尉を名乗る。 |
| 二代 | 三田村左衞門尉幸真 | 承久の乱(1221年)で後鳥羽上皇方に味方した城主が討ち死にした。後任として佐々木家から定義が派遣される。 |
| 三代 | 三田村左衞門尉康家 | 近江守護京極持清の命により三田村の地頭職として赴任。亀若丸(浅井重政)を育てる。居館の新築。 |
| 四代 | 三田村左衞門尉友家 | 応仁の乱に巻き込まれる。京極家の家督相続をめぐる内紛が始まる。越前に逃れ定着する。 |
| 五代 | 三田村左衞門尉康定 | 六角氏の浅井氏総攻撃で三田村氏は浅井と六角方に二分し、城主は六角方になった。康定亡き後、義弟の忠政は浅井氏側につく。以後、浅井氏に肩入れするものが三田村家の主流となる。 |
| 六代 | 三田村左衞門尉氏光 | 清水谷に屋敷を設ける。浅井家との血縁関係深まる。六角氏と決別し浅井氏の筆頭家臣となる。波切小車紋に変更 |
| 七代 | 三田村伊予守定頼 | このときに城主家の交代があった→左衞門尉から伊予守へ官職が変わっている。浅井亮政の娘と結婚。 |
| 八代 | 三田村飛騨守光頼 | 官名変更→城主家の交代。浅井家と信長の同盟を強力に推進。浅井家では三田村氏が筆頭家臣として重んじられる。 |
| 九代 | 三田村相模守定元 | 官名変更→城主家の交代。箕作城攻撃戦で秀吉の身代わりに戦死。浅井長政が三田村まで足を運び、定元の遺髪と槍を届ける。 |
| 十代 | 三田村多賀備中守国定 | 姉川合戦で三田村城は朝倉氏の本陣として使用されたが、朝倉軍の敗退で落城。以後は廃城となる。浅井長政と命運をともにする。国定は信長の裁定で斬首刑。 |
中世の御家人の館
御家人(武士)は、土地を支配するために、領内の交通の要衝などの重要な場所に、土塁・堀などに囲まれた館を造り住みました。
御家人などの武士が住んでいた屋敷のことを「居館」と呼んでいます。居館は堀ノ内・館・土居などとも呼ばれます。館の周囲に、田畑の灌漑(農作物のために人工的に田畑へ水を供給)用の用水を引いた方形の水堀を設け、この堀を掘った土で盛り上げた土塁で囲んだ中に、居住する場所を構えました。
館は、住居としての役割のほか、戦に備えた城や砦の役割を持っていました。入口には門を構え、出入りや荷物を点検する番人が休むことなく見張ていました。
館の中心建物が主屋(主人や家族が住む、敷地内の中心になる建物)と副屋(妻や子女が住む主屋とは別棟の建物)で、人と対面する施設としても利用されました。現在の台所である厨、燃料を保管する薪小屋、武器庫や納屋(屋外に建てられた物を納めておく小屋)、蔵、また、持仏堂(毎日拝む仏像や先祖の位牌を安置しておく場所)のような宗教施設が置かれる事もありました。
この他、田畑や、郎従(主従関係によって仕えた家来)などが住む遠侍(主屋から遠く離れた場所に設けられた警護の武士の詰め所)や厩も併設されました。田畑は、農民の夫役(労働で治める税金)を使い耕作させていました。馬は、戦や荷物の運搬に欠かすことの出来ない大切な生き物で、屋敷内で飼われていたのです。こうした館の構造が、文献や絵図から推定されます。
三田村城からの史跡巡り
散策コース1時間 ①三田村城跡→②七十士の墓→③野神塚古墳
探索コース3時間 ①三田村城跡→②竜ヶ鼻(茶臼山古墳)→③遠藤直経の墓→④陣杭の柳→⑤勝山
→⑥姉川戦死者の供養碑→⑦血川の跡地→⑧陣田
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
