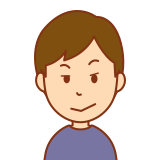乾坤一擲の一冊 世に問う!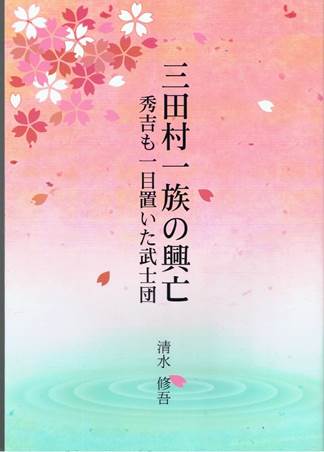
三田村氏館跡:歴史遺産としての現状と未来への願い
概要
滋賀県長浜市三田町にある真宗大谷派の寺院「傳正寺」は、一辺100メートル、高さ4メートルほどの土塁に囲まれた要塞のような姿を残しています。この地は、俳優・三田村邦彦氏がルーツを探ったことでも知られ、三田村姓の発祥地とされています。
歴史的背景と史跡指定
- 1990年代初頭、三田村氏のルーツ調査がきっかけで、この地の歴史的価値が注目されました。
- 長浜市教育委員会による調査の結果、三田村左衛門の城郭であることが判明しました。
- 2006年、三田村氏館跡は国の史跡に指定され、地域は祝賀ムードに包まれました。
現在の課題と将来への展望
- 史跡指定から20年が経過し、住民の関心が薄れ、案内板も色褪せるなど、歴史遺産としての意識が風化しつつあります。
- 特に若い世代の関心の低さが懸念されています。
- 史跡の維持と、高齢化が進む三田町の発展の起爆剤として、この歴史遺産を地域活性化に活用することが期待されています。
- 先人たちの功績をたどり、三田町の歴史を後世に伝える責任を痛感しています。
書籍の紹介
本書は、古代のロマンあふれる三田村を舞台に、佐々木幸弼による地頭職赴任(1200年)から姉川合戦(1570年)までの370年間を、事実80%・フィクション20%の割合で描いています。鎌倉幕府の安定に貢献した佐々木氏と三田村氏の功績を顕彰し、中世の歴史をリアルに体験できるストーリー仕立てとなっています。
読書の楽しみ方・・・本書を愛読して頂くには中世社会に溶け込むことがストーリーをおもしろくさせてくれます。現代とは異次元の中世社会の人々は物理的制約や思考の限界の中で知恵を絞り肉体を追い込んで困難に臨み、ある者は死にある者は生き延びたのです。登場人物には現代的な思考を持たせず、当時の文化や価値観を忠実に再現。時代小説の醍醐味である「その時代への没入」を徹底しています。つまり現代的に考えさせることが内容をつまらなくすると考えます。本書に登場する人物たちの振る舞いは、現代人から見れば何と非常なとか、何と哀れなとか、何と命の軽いこととか、反対に何と美しいのか、様々な感情を抱かせますが、これがこの時代の流儀であり、ありふれた感覚でした。執筆中は中世社会にタイムスリップし、当時の武士や農民になりきって思考し行動し会話を楽しみました。時代小説の醍醐味はその時代へ読者も入り込むことです。
■「紙の本」によって得られる“体験”
情報が洪水のように押し寄せる今だからこそ、本当に大切なのは「質の高い情報を深く味わう力」。その力を鍛える最強のツールが、実は紙の本なのです。
紙媒体で味わえる「ページを繰るドキドキ感」や「指先で紙の質感を確かめる楽しさ」は、デジタル端末では得ることが難しいと感じる人も少なくないのではないでしょうか。
また紙の本で読むと、「あの話、確か本の真ん中あたりで読んだ気がする」「重要な部分は右ページの下にあったな」など、内容とページの位置が自然と頭に残ります。付箋を貼った場所や、折り目のついたページ、インクの匂いや手触りまで、記憶と結びつく「手がかり」をたくさん作れるのは紙の本ならではです。
そしてこの、紙媒体で五感をフル活用して本と向き合う「没入体験」こそが、実は内容の深い理解や記憶の定着を助けてくれることが、脳科学的にも明らかになっているのです。
あらすじ(3,000字)をご覧下さい。・・・本文は90,000字です。
『湖北に咲いた忠義の華:三田村一族一千年の興亡史』
第一章:渡来の知恵と「三田国」の黎明
三田村一族のルーツは、3世紀初め、朝鮮半島南部の戦乱を逃れて近江(滋賀県)へ渡来した「三田(みた)氏」にまで遡ります。彼らは当時の最先端技術である製鉄と稲作の知識を持っていました。
当時の近江湖北、姉川流域は原生林が広がる未開の地でしたが、三田氏は土質の良さを見抜き、自作の鉄製農具で開墾を開始しました。彼らは自分たちの技術を独占せず、周辺住民に惜しみなく伝授したため、一帯は良質な米の産地へと変貌します。これが現代の「近江米」の原種となりました。
地域住民の信頼を得た三田氏は、単なる渡来人集団を超え、周辺のムラを束ねる「三田国」の首長となります。彼らは野(の)神(がみ)(田の神)を篤く信仰し、呪術的な権威も持つシャーマン的な統治者として、戦乱ではなく平和的な信頼関係によって小国を治めました。ヤマト政権成立後も「首(おびと)」の姓を授かり、中央政権とは適度な距離を保ちながら、地方の有力豪族としての地位を固めていきました。
第二章:鎌倉の風と「三田村」への改姓
平安時代、律令制の崩壊とともに三田氏は、土地を国司の横暴から守るため、権威ある京都の「東寺」に名目上の領有権を寄進し、自らは実質的な管理職である「荘官」として三田村を維持し続けました。
大きな転換点は鎌倉時代初期です。源頼朝の有力御家人であり、近江守護を務める佐々木氏の一族・「佐々木幸(こう)弼(すけ)」が三田村の地頭として赴任しました。幸弼は当初、余所(よそ)者として警戒されましたが、代々この地を守ってきた三田氏の当主・藤太(後の北川氏)と深く対話し、協力体制を築きます。
幸弼が下した最大の決断は、名門「佐々木」の姓を捨て、村の名前である「三田村」へ改姓したことでした。これは「この地に骨を埋め、農民と共に生きる」という強い覚悟の表明でした。幸弼は村を「九つの里」に分ける計画的な区画整理を行い、姉川から新たな水路を引いて灌漑設備を一新しました。この「名君あって良民あり」と称えられた統治の精神は、後の三田村家へ脈々と受け継がれていくことになります。
第三章:三田村家の再興と浅井家との絆
承久(じょうきゅう)の乱(らん)(1221)による一時的な断絶を経て、室町時代(1336~1573)に京極家から派遣された康家が三田村家を再興します。康家は延暦寺や堅田衆といった近隣勢力との紛争を解決する一方で、ある重要な役割を果たしました。それは、後に北近江の戦国大名となる浅井家の始祖・「亀若丸(後の浅井重政)」を、養子同然に三田村の地で育て上げたことです。
この深い縁により、三田村一族は京極家の重臣でありながら、次第に実力を蓄える浅井家の強力な支持基盤となっていきました。戦国時代が幕を開けると、三田村家は浅井家の筆頭家臣として、軍事・政治の両面で主家を支える存在となります。
第四章:信長の台頭と秀吉との奇縁
戦国時代(1467~1573)、八代目当主・光頼は、浅井家と織田信長の同盟を強力に推進しました。この同盟により、長政は信長の妹・お市を妻に迎え、浅井家は全盛期を迎えます。しかし、信長が浅井家の古くからの同盟国である朝倉氏を独断で攻めたことで、同盟は崩壊します。
この激動の時期、九代目当主・定元は数々の逸話を残しています。特に有名なのが、織田軍の攻撃を受けた箕作(みつくり)城(じょう)の戦いです。この際、定元は敵方であった六角氏の軍勢が放った矢から秀吉(羽柴秀吉)を守ろうとし、討ち取られてしまいました。秀吉の身代わりとなって戦死したと伝えられています。これは単なる武勇伝ではなく、戦場における武士同士の奇妙な縁や、三田村家が持つ「忠義」と「情」の深さを物語るエピソードとして語り継がれています。
第五章:姉川の合戦と三田村城の落城
元亀元年(1570年)、ついに浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍が激突する姉川の合戦が勃発します。
三田村家の居城である三田村城は、姉川の北岸に位置し、合戦時には朝倉景(かげ)健(たけ)率いる朝倉軍一万余の本陣として使用されました。三田村一族は、自分たちの生活の場であり先祖代々の守りである城が戦場となる中、浅井・朝倉の勝利を信じて死力を尽くしました。
しかし、戦況は織田軍の猛攻の前に暗転します。朝倉軍が敗退し、戦火は三田村城にも及びました。要塞としての機能も備えていた居館でしたが、多勢に無勢、城は炎上し落城しました。これ以降、三田村城が再建されることはなく、歴史からその姿を消すこととなりました。

第六章:国定の殉死と一族の終焉
浅井家最後の当主・浅井長政は小谷城へと退き、最後まで信長に抵抗しました。この絶望的な状況下で、三田村家十代目当主・国定は、主家への忠義を貫き通します。
国定は長政とともに小谷城に籠城し、織田軍の包囲網の中で孤軍奮闘しました。しかし、天正元年(1573年)、小谷城は陥落し、長政は自害。国定は捕らえられ、信長の前へと引き出されました。信長は、かつて三田村家が同盟を推進していたことや、定元が秀吉の身代わりとなった過去を知りつつも、徹底抗戦を選んだ国定を許しませんでした。
信長の裁定により、国定は斬首に処されました。古代の渡来から始まり、湖北の地を耕し、武士として繁栄した三田村一族は、ここに主家と運命を共にする形で滅亡しました。
結びに:大地に残された一族の魂
三田村一族の物語は、悲劇的な滅亡で終わります。しかし、彼らが残したものは決して小さくありません。
初代・幸弼が整備した「九つの里」という村の形は、近世以降も三田の村づくりの基本となりました。また、彼らが命をかけて守ろうとした姉川の水利体系は、その後の湖北農業の基盤として、数百年以上にわたり農民たちの暮らしを支え続けました。
主君に殉じた国定の忠義、浅井長政との深い絆、そして戦場の霧の中に消えた秀吉との因縁。それらはすべて、かつてこの地に生きた人々の情熱の証です。三田村一族が切り拓いた豊かな水田は、今も変わらず湖北の地を黄金色に染め、一千年の歴史を物語っています。
ご購入について
書籍: A5版/152ページ
価格: 1,500円(+送料200円)
PDF版: 1,000円・・・メールにPDFファイルを添付
30冊以上: 送料無料+現地ガイド(長浜駅西口より送迎バス)
申込先:〒526-0242 滋賀県長浜市三田町513
清水 修吾(℡ 0749-74-2998) 葉書・電話・メールでお求め下さい。スマートレター便で即日発送します。